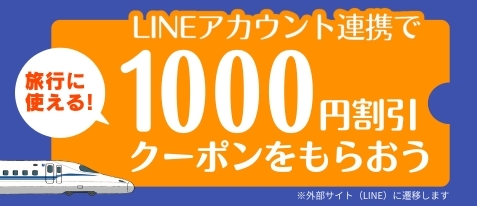延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京として遷都して以来、1000年以上にわたり京都は日本の中心として栄えてきました。そんな長い歴史を持つ京都は、平安時代から江戸時代までの貴重な文化遺産の神社や寺院を数多く残り、日本の歴史や文化を今に伝えています。また、神聖な雰囲気に包まれる「パワースポット」としてもよく知られています。しかし数が多いからこそ、どこの神社や寺院を訪れたらよいのか迷ってしまうという人も少なくないのではないでしょうか。
今回は、京都の数ある神社や寺院の中から29の神社・寺院を厳選してご紹介します。どの社寺も歴史の重みや神聖な雰囲気、美しい景観を堪能できる神社・寺院ばかりです。それぞれの歴史やご利益、見どころなど詳しくお伝えしていきますので、ぜひ京都旅行の参考にしてください。
- 【長寿・恋愛・学業成就】四季折々の絶景と3つのご利益 「清水寺」
- 【五穀豊穣・商売繁昌】千本鳥居と稲荷山の神秘 「伏見稲荷大社」
- 【美容祈願】祇園造と紅葉が輝く祇園を代表する神社 「八坂神社」
- 【学業成就】歴史と季節が彩る学問の神様と梅の名所 「北野天満宮」
- 【縁結び】1200年前の古都を体感!朱色の社殿と大鳥居が魅力 「平安神宮」
- 【縁結び】水の神を祀る神秘的なパワースポット 「貴船神社」
- 格式高い禅寺と紅葉が織りなす絶景 「南禅寺」
- 【除災・延寿】平安京の記憶と五重塔の圧巻の姿 「東寺」
- 【縁結び・美麗祈願】糺の森で心身ともに清める 「賀茂御祖神社(下鴨神社)」
- 【火防】京都市最高峰の霊山にそびえる全国約900社の総本社 「愛宕神社」
- 【厄除・勝運】楼門と紅葉の調和は圧巻 「賀茂別雷神社(上賀茂神社)」
- 【縁結び】悪縁を断ち良縁を結ぶ SNSでも評判の神社 「安井金比羅宮」
- 【極楽往生・現世安穏】極楽浄土を映す鳳凰堂と四季折々の美 「平等院」
- 【勝運・金運】通天橋から望む紅葉の渓谷と禅の調和 「東福寺」
- 【健康】わらべ地蔵と苔の庭園が心癒す 「三千院」
- 【開運】京都最古の禅寺と趣の異なる庭園、紅葉が彩る 「建仁寺」
- 【魔除け・厄除け】安倍晴明公を祀り平安の祈りが息づくパワースポット 「晴明神社」
- 【厄除開運】霊水が湧き出る八幡造りの荘厳な社殿 「石清水八幡宮」
- 【開運】雲龍図の迫力と広大な庭園の世界遺産 「天龍寺」
- 樹齢400年以上の巨木と極楽浄土を思わせる御影堂が迎える 「西本願寺」
- 【金運】黄金の鳥居と福包み守りがツキを呼び込む 「御金神社」
- 【健康】阿呆賢さんに願いをこめる 「今宮神社」
- 【方除】源氏物語ゆかりの庭園が美しい平安京の守護 「城南宮」
- 【学業成就・芸能】祈念神石が導く願いの成就、芸能人も訪れるパワースポット
「車折神社」 - 【お酒の神】延命長寿の霊泉と醸造の祖神を祀る 「松尾大社」
- 【諸願成就】四柱の神々と霊石の力が守護する 「平野神社」
- 【勝運】皇室ゆかりの古社で12柱の神々を祀る 「藤森神社」
- 【出世開運】豪華な唐門と豊臣秀吉公像が参拝者を迎える 「豊国神社」
- 【学業成就・良縁】かわいいうさぎに願いを託す 「宇治上神社」
- 京都旅行を予約するならJR東海ツアーズの新幹線パックがおすすめ
- まとめ
【長寿・恋愛・学業成就】四季折々の絶景と3つのご利益 「清水寺」


「清水寺」は、宝亀9年(778年)に開創された由緒ある寺院で、その歴史と文化的価値から1994年にはユネスコ世界文化遺産「古都京都の文化財」のひとつとして登録されました。
見どころは、本堂の「清水の舞台」で、釘を使用しない「懸け造り」と呼ばれる伝統的な建築技法が用いられています。崖からせり出した地上約13mの舞台からは京都市内を一望でき、特に桜の季節や紅葉の時期の眺めはまさに絶景です。また、清水寺開創の起源であり寺名の由来ともいわれる「音羽の滝」は、「延命長寿」「恋愛成就」「学業成就」などのご利益があるとされる清水が3筋に分かれて流れています。
清水寺を訪れるなら、参拝客の比較的少ない早朝がおすすめです。朝の澄んだ空気の中での参拝は静寂と荘厳さをよりいっそう感じられることでしょう。また、春、夏、秋に催される夜間特別拝観もおすすめで、幻想的にライトアップされた境内を楽しむことができ、昼間とはまた違った美しい清水寺に出会えます。
| 所在地 | 〒605-0862 京都府京都市東山区清水1丁目294 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-551-1234 |
| アクセス | 京都市営バス「五条坂」下車、徒歩約10分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【五穀豊穣・商売繁昌】千本鳥居と稲荷山の神秘 「伏見稲荷大社」


和銅4年(711年)に創建された「伏見稲荷大社」は、全国に約3万社ある稲荷神社の総本宮で、古くから五穀豊穣の神様として信仰されてきました。さらに商売繁昌、家内安全、病気平癒、諸願成就といったご利益もあるとされ、訪れる人々の心の拠り所となっています。
特に有名なのが「千本鳥居」で、赤い鳥居が連立する光景は「圧巻」のひと言です。その日本的な美しさは多くの人々を魅了し、SNSでも多く取り上げられています。昼間は人が絶えないので、千本鳥居の写真を撮りたい場合は、参拝者が比較的少ない早朝に訪れるのがおすすめです。
千本鳥居をくぐり抜けると、「奥社奉拝所」(通称:「奥の院」)があります。神々しい雰囲気が漂うパワースポットとしても知られる奥の院は、稲荷山の神々を拝むための場所です。右奥には一対の石灯篭「おもかる石」があり、願いを思い浮かべながら石を持ち上げ、予想よりも軽ければ願いが叶うとされています。
なお、運気をさらに高めたい人は、稲荷山を巡拝する「お山めぐり」にも挑戦してみましょう。山頂まで足を延ばすことでさらにご利益を得られるとされています。なかでも、神々が降り立った地として伝わる「一ノ峰(上社神蹟)」は、稲荷山で一番のパワースポットです。四季折々の自然を楽しみつつ山頂まで参道を進めば、神聖な空気に包まれて身も心も満たされることでしょう。
| 所在地 | 〒612-0882 京都府京都市伏見区深草薮之内町68番地 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-641-7331 |
| アクセス | JR「稲荷駅」下車すぐ 京阪本線「伏見稲荷駅」下車、徒歩約5分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
京都のSNS映えスポットについては
こちらの記事でもご紹介しています。
【美容祈願】祇園造と紅葉が輝く祇園を代表する神社 「八坂神社」


「八坂神社」は、日本全国に約2,300社ある八坂神社や「素戔嗚尊(すさのおのみこと)」を祭神とする神社の総本社で、地元では「祇園さん」の愛称で親しまれています。国宝に指定されている本殿は、本殿と拝殿を単一の屋根で覆う「祇園造」と呼ばれる独特の建築様式で有名です。また、現在は漆喰で固められており見ることはできませんが、本殿の下には「青龍」の棲む龍穴として伝わる池があり、京都有数のパワースポットのひとつとされています。
境内に20社近くある社殿には、厄除け、縁結び、美容などそれぞれさまざまなご利益があるといわれています。なかでも特に女性たちの注目を集めているのが、美の神を祀る「美御前社(うつくしごぜんしゃ)」です。社殿前から湧き出るご神水「美容水」を肌に数滴つけると心身ともに美しくなるという言い伝えがあり、多くの女性が参拝に訪れます。
八坂神社の魅力がもっとも増すのは、祭りの季節と紅葉の季節です。夏には京都三大祭りのひとつである「祇園祭」が行われ、豪華絢爛な「山鉾巡行(やまほこじゅんこう)」や「宵山(よいやま)」を一目見ようと多くの人が訪れます。また、秋には美しい紅葉が楽しめ、特に本殿裏の参道にある通称「もみじのトンネル」は必見です。神社の厳かな景観に鮮やかな紅葉が映え、美しい写真が撮れるスポットとしても人気を博しています。
| 所在地 | 〒605-0073 京都府京都市東山区祇園町北側625 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-561-6155 |
| アクセス | 京阪電車「祇園四条駅」下車、徒歩約5分 京都市営バス「祇園」下車すぐ |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【学業成就】歴史と季節が彩る学問の神様と梅の名所 「北野天満宮」


「北野天満宮」は、学問・厄除・芸能の神様として御祭神菅原道真公を祀る、全国に12,000社ある天満宮・天神社の総本社です。1年を通じて多くの参拝者が訪れますが、特に受験シーズンになると受験合格を祈願する全国の受験生たちで賑わいます。
菅原道真公を祀る御本殿と拝殿を含む御社殿は日本最古の八棟造で、現在の建物は慶長12年(1607年)に豊臣秀頼公によって再建されたものです。桃山時代の華やかで豪華な様式を用いた神社建築の貴重な遺構として、国宝に指定されています。また、楼門と拝殿をつなぐ三光門も、同様に桃山時代の建築様式が色濃く見られるとして、国の重要文化財に指定されました。
菅原道真公の誕生日の6月25日と祥月命日の2月25日にちなみ、毎月25日には「御縁日」が催されます。参道には多くの露店が並び、大勢の参拝者で賑わう様子は、この日ならではの光景です。夜には約350基の石燈籠と約250基の釣燈籠が一斉に灯り、境内は昼間とは異なる幻想的な雰囲気に包まれ、訪れる人々を魅了します。
また、北野天満宮は梅の名所としても名高く、写真映えスポットとしても人気です。例年12月中旬から3月末にかけて境内にある菅原道真公ゆかりの梅50種約1,500本をはじめとして紅白の梅が咲き誇り、境内を華やかに彩ります。
| 所在地 | 〒602-8386 京都府京都市上京区馬喰町 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-461-0005 |
| アクセス | 嵐電北野線「北野白梅町駅」下車、徒歩約5分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【縁結び】1200年前の古都を体感!朱色の社殿と大鳥居が魅力 「平安神宮」


「平安神宮」は、1895年に平安京遷都1100年を記念して設立された神社で、平安京の「朝堂院(ちょうどういん)」を再現した美しい朱色の社殿群が特徴です。境内に入ると、古都・京都の開放的な風景が広がり、まるで平安時代にタイムスリップしたかのような感覚を味わえます。
御祭神は、平安京の創始者である「桓武天皇」と、平安京最後の天皇「孝明天皇」の2柱で、縁結びのパワースポットとしても有名です。ほかにも、開運招福、商売繁盛、厄除け、学業成就などのご利益もあるとされています。
平安神宮のシンボルとしてひときわ存在感を放つ高さ24.2mの大鳥居は、美しい朱色が魅力的でフォトスポットとしても人気を博しています。さらに、社殿を囲むように東・中・西・南の4つの庭を配置されている「平安神宮神苑」では、春の紅しだれ桜、初夏の杜若・花菖蒲、秋の紅葉、冬の雪景色と、風光明媚な四季折々の趣を楽しむことができます。
| 所在地 | 〒606-8341 京都府京都市左京区岡崎西天王町97 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-761-0221 |
| アクセス | 京都市営バス「岡崎公園美術館・平安神宮前」下車、徒歩約5分 |
|
※平安神宮は、2025年に御鎮座130年を迎えます。この節目に合わせた記念事業として、社殿の塗り替えが2024年~2030年末ごろまで、チンチン電車の修繕が2024年~2026年3月ごろまで進められています。最新情報は公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【縁結び】水の神を祀る神秘的なパワースポット 「貴船神社」


「貴船神社」は、全国に点在する約500社の貴船神社の総本宮で、平安時代から続く歴史ある神社です。御祭神は「高龗神(たかおかみのかみ)」で、水の供給をつかさどる神とされています。水神を御祭神としているため、水が濁らないようにという意味から、「きぶね」ではなく「きふね」と発音されます。
境内に足を踏み入れると、本宮社殿前の石垣から湧き出るご神水が参拝者を出迎えてくれます。この貴船山の自然の恵みのご神水は、夏に訪れるとなんとも涼やかな癒しをもたらしてくれます。また、ご神水に白紙のおみくじを浮かべると文字が浮き上がる「水占みくじ」も人気です。
また、本宮から少し歩むと「結社」があり、こちらには縁結びの神様として名高い「磐長姫命(いわながひめのみこと)」が祀られています。恋愛成就を願う多くの参拝者が訪れ、緑色の「結び文」に自身の願いを記して「結び処」に結びつけると願いが叶うとされています。
| 所在地 | 〒601-1112 京都府京都市左京区鞍馬貴船町180 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-741-2016 |
| アクセス | 叡山電鉄鞍馬線「貴船口駅」下車、徒歩約30分 京都バス「貴船」下車、徒歩約5分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
京都の観光名所や穴場については
こちらの記事でも紹介しています。
京都旅行にはJR東海ツアーズのプランがおすすめです。
格式高い禅寺と紅葉が織りなす絶景 「南禅寺」

「南禅寺」は、臨済宗南禅寺派の総本山であり、その歴史は鎌倉時代末期の寛政3年(1291年)に遡ります。亀山法皇によって創建された南禅寺は最も格式の高い禅寺で、ご本尊は釈迦牟尼仏です。
境内全体が国の史跡に指定されており、国宝の「方丈」や、重要文化財の「三門」、国名勝の「方丈庭園」など、多くの文化遺産を擁しています。なかでも三門は日本三大門のひとつに数えられ、その壮大さで見る者を圧倒します。上部に登ることも可能で、三門上部からの眺望は息をのむほどの美しさです。
また、境内には約300本ものカエデが植えられており、11月中旬から12月上旬にかけては美しい紅葉も楽しめます。三門周辺や、三門から法堂(はっとう)へと続く参道沿い、琵琶湖疏水にかかるレンガでできたアーチ状の水路閣周辺など、境内のさまざまな場所に美しい紅葉が点在しています。
| 所在地 | 〒606-8435 京都府京都市左京区南禅寺福地町86 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-771-0365 |
| アクセス | 地下鉄「蹴上駅」下車、徒歩約10分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【除災・延寿】平安京の記憶と五重塔の圧巻の姿 「東寺」

「東寺」は、現存する唯一の平安京の遺構であり、正式名称は「教王護国寺」です。1994年に世界遺産に登録されました。
境内に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのは高さ54.8mを誇る五重塔です。この塔は、日本一高い木造建築物であるとともに、東寺ひいては京都のシンボルとしてその存在感を放っています。そのほかにも、弘法大師空海の住まいだった「御影堂(みえいどう)」、密教の教えを視覚的に表現した「立体曼荼羅(りったいまんだら)」など、境内には、東寺の歴史や真言宗の教えを感じられる貴重な建造物や寺宝が満載です。毘沙門堂の横には、「尊勝陀羅尼(そんしょうだらに)の碑」と呼ばれる神聖なる碑があり、触れると除災・延寿のご利益があると伝えられています。
東寺はまた、季節の美しさを感じられる場所としても広く知られており、春には桜が咲き乱れ、秋には木々が色とりどりの紅葉を見せてくれます。シーズン毎に催される夜間特別拝観では、ライトアップされた約200本の桜や約250本もの紅葉と五重塔が織りなす幻想的な景色が広がり、訪れる人々を魅了しています。
| 所在地 | 〒601-8473 京都府京都市南区九条町1番地 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-691-3325 |
| アクセス | JR「京都駅」下車、徒歩約15分 |
【縁結び・美麗祈願】糺の森で心身ともに清める 「賀茂御祖神社(下鴨神社)」


「賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)」は、通称「下鴨神社」として親しまれており、平安京造営の際に国家鎮護の神社として朝廷の崇敬を集めた由緒正しい神社です。賀茂川の下流に位置しており、深い歴史と文化的価値からユネスコの世界文化遺産に登録されています。
まず参道に足を踏み入れると、「糺(ただす)の森」と呼ばれる豊かな自然が一面に広がります。糺の森では四季折々に美しい景観を楽しむことができ、特に木々が鮮やかな緑に染まる初夏は、参道が緑のトンネルに包まれ心が洗われるような美しさです。
そして、本殿近くにある「御手洗(みたらし)池」では、「水みくじ」と呼ばれる独特のおみくじが体験できます。池の水におみくじの紙を浸すと徐々に占いの結果が浮かび上がってくるというワクワク感があり、参拝客に人気です。
また、下鴨神社の摂社「河合神社」は、女性守護として広く信仰されています。この神社は美麗の神として名高い「玉依姫命(たまよりひめ)」をご祭神としており、「鏡絵馬」という絵馬に自分の化粧品でメイクし願いを込めると、外見だけでなく内面も美しくなるといわれています。
さらに、下鴨神社の末社「相生社(あいおいのやしろ)」は、縁結びのパワースポットとして有名です。縁結びのほかにも、安産や育児、家庭円満などのご利益があると言い伝えられており、人生の節目に訪れる参拝客で賑わいます。
| 所在地 | 〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町59 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-781-0010 |
| アクセス | 京都市営バス「下鴨神社前」下車、徒歩約3分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【火防】京都市最高峰の霊山にそびえる全国約900社の総本社 「愛宕神社」


京都市最高峰の霊山である愛宕山の山頂に鎮座する「愛宕神社」は、全国に約900社ある愛宕神社の総本社です。火の神を祀っており、古くから火災除けの御利益がある神社として多くの人々に親しまれてきました。「火迺要慎(ひのようじん)」のお札は特に有名で、火災防止のお守りとして人気を博しています。
愛宕神社には年間を通じて多くの参拝者が訪れますが、なかでも多くの人が訪れるのが毎年7月31日の夜から8月1日の早朝にかけて行われる「千日詣(せんにちまいり)」です。正式には「千日通夜祭(せんにちつうやさい)」と呼ばれ、この期間にお参りすると1000日分の御利益があるとされているため、毎年数万人の参拝者が訪れます。また、3歳までの子どもがこの日に参拝すると、その子は生涯、火の災難から守られると信じられており、お子様連れの家族も多く訪れます。
ただし、愛宕神社へは、最も一般的な登山ルートである表参道でも、清滝の登山口から山頂まで片道約2~3時間かかります。そのため、参拝は必ず午前中にスタートし、明るく安全な時間帯に登山を終えることができるように注意しましょう。また、道中は自然豊かな景色を堪能できる一方で、ところどころ険しい箇所もありますので、登山に適した装備とともに体力や体調なども考慮して参拝するようにしてください。
| 所在地 | 〒616-8458 京都府京都市右京区嵯峨愛宕町1 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-861-0658 |
| アクセス | 京都バス「清滝」下車、徒歩約2~3時間 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
おトクな旅行の情報や割引クーポンを配信中
LINEアカウント連携で1,000円クーポンをゲット♪
※外部サイト(LINE)に遷移します。
【厄除・勝運】楼門と紅葉の調和は圧巻 「賀茂別雷神社(上賀茂神社)」


「賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)」、通称「上賀茂神社」は、京都の緑豊かな地に位置し、古くから人々に愛されてきた歴史ある神社です。御祭神は「賀茂別雷大神」で、厄除・災難除け・必勝の神として信仰されてきました。
賀茂別雷神社は広大な自然と深い歴史が交錯する場所としても知られており、境内全域が「古都京都の文化財」としてユネスコの世界文化遺産に登録されています。国宝2棟、重要文化財41棟と数々の文化財を擁しており、なかでも重要文化財の「楼門」は、撮影スポットとしても人気です。朱色の外観が極めて美しく、賀茂別雷神社の象徴となっています。
御祭神を祀る本殿は、神社建築様式のひとつである「流造(ながれづくり)」の典型として国宝に指定されています。社殿の壁には、狩野派によって描かれた「影狛(かげこま)」と呼ばれる狛犬の絵が残されており、こちらは日本絵画史においても大変貴重なものとされています。
また、賀茂別雷神社は紅葉が美しいことでも有名で、境内にある「ならの小川」では秋になると真っ赤な紅葉が小川を覆い尽くします。その幻想的な光景は、まさに圧巻のひと言です。
| 所在地 | 〒603-8047 京都府京都市北区上賀茂本山339番地 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-781-0011(電話受付時間8:30~17:00) |
| アクセス | 京都市営バス「上賀茂神社前」下車すぐ |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
京都の紅葉スポットについては
こちらの記事でもご紹介しています。
【縁結び】悪縁を断ち良縁を結ぶ SNSでも評判の神社 「安井金比羅宮」


「安井金比羅宮(やすいこんぴらぐう)」は、「縁切り神社」として広く親しまれている歴史ある神社です。
藤原鎌足が一族の繁栄を祈り、寺院「藤寺」を建立したことを起源とします。本殿には、主祭神である「崇徳(すとく)天皇」、「大物主神(おおものぬしのかみ)」、「源頼政」公の3柱が祀られています。崇徳天皇が配流となった際、讃岐の金刀比羅宮ですべての欲を断ち切り祈りを捧げたことから、断ち物・縁切りの祈願所として信仰されてきました。人間関係の縁をはじめ、病気、酒、煙草、賭事など、幸せの妨げとなるあらゆる悪縁を断ち切り、新たな良縁を引き寄せるといわれています。
境内には、高さ1.5m、幅3mの絵馬のような形をした「縁切り縁結び碑」と呼ばれる石があり、参拝者に人気です。碑の中央に穴が開いており、この穴をくぐることで悪縁を断ち、良縁を引き寄せるといわれています。まず本殿を参拝し、願い事を書いた「形代(かたしろ)」(身代わりのおふだ)を持って碑の表から裏へ穴をくぐり(悪縁を断つ)、次に裏から表へ穴をくぐり(良縁を結ぶ)、最後に手にしていた形代を碑に貼り願いを託すのが祈願方法のひとつです。
なお、「縁切り縁結び碑」での御祈願は24時間可能ですので、混雑を避けて参拝・祈願を行いたい方は、比較的空いている早朝や夕方以降がおすすめです。
| 所在地 | 〒605-0823 京都府京都市東山区東大路松原上ル下弁天町70 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-561-5127 |
| アクセス | 京都市営バス「東山安井」下車、徒歩約1分 京阪本線「祇園四条」駅下車、徒歩約10分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【極楽往生・現世安穏】極楽浄土を映す鳳凰堂と四季折々の美 「平等院」

「平等院」は、永承7年(1052年)、藤原道長の子である藤原頼通公によって創建された寺院で、「古都京都の文化財」のひとつとしてユネスコの世界文化遺産に登録されています。平等院が創建された翌年には、平等院最大の見どころであり極楽浄土を具現化したといわれる「鳳凰堂」が建てられました。鳳凰堂は十円硬貨の表に描かれており、国宝にも指定されています。
屋根の上に金色の鳳凰が輝く鳳凰堂は池に浮かんで見えるように建てられているのが特徴で、まるで極楽に築かれた宮殿のような美しさが魅力です。1000年近い歴史を経てもなお悠久の時の輝きを放ち続けるその姿は、人々の心に深く刻み込まれます。
また、平等院は桜や紅葉の名所としても有名です。春には桜が美しく咲き誇り、秋にはカエデが平等院全体を紅に染め上げます。特に鳳凰堂周辺の桜や紅葉が池に映る姿は得もいわれぬ美しさで、訪れる人々を魅了しています。
| 所在地 | 〒611-0021 京都府宇治市宇治蓮華116 |
|---|---|
| 電話番号 | 0774-21-2861 |
| アクセス | JR「宇治駅」下車、徒歩約10分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【勝運・金運】通天橋から望む紅葉の渓谷と禅の調和 「東福寺」


「東福寺」は臨済宗東福寺派の大本山の寺院で、嘉禎2年(1236年)から建長7年(1255年)の約19年という長い歳月を費やし、摂政九條道家によって建立されました。
広大な伽藍を有することで知られており、国宝に指定されている「三門」や、龍の天井画で名高い「法堂(はっとう)」など、歴史的な趣を感じさせる壮大な建築物が境内に点在しています。「本坊庭園(方丈)」は大方丈を中心に東西南北に広がる4つの庭園からなり、釈迦の生涯を表す8つの場面になぞらえた「八相の庭」として有名です。
また、東福寺は紅葉の名所でもあり、「通天橋」や「洗玉澗(せんぎょくかん)」から眺める紅葉は息をのむほどの美しさです。加えて、東福寺の塔頭(たっちゅう)である「勝林寺」は、勝運や金運のご利益があるとされているので、あわせて参拝してみてはいかがでしょうか。
| 所在地 | 〒605-0981 京都府京都市東山区本町15町目778 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-561-0087 |
| アクセス | JR「東福寺駅」下車、徒歩約10分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【健康】わらべ地蔵と苔の庭園が心癒す 「三千院」


「三千院」は、延暦年間(782年~806年)に比叡山東塔南谷(とうとうみなみだに)の梨木の下に伝教大師最澄が一字を構えたことを起源とします。病気平癒のご利益があるとされ、阿弥陀三尊像をはじめとする文化財や、聚碧園(しゅうへきえん)といった美しい名園を擁することでも有名です。
国宝に指定されている阿弥陀三尊像は、重要文化財の「往生極楽院」に祀られています。往生極楽院は、お堂より大きい阿弥陀三尊像を納めるために天井が舟底型に設計されているのが特徴で、そこに描かれた天女の舞や菩薩など極楽浄土の情景は神々しく荘厳です。
往生極楽院の南側に位置する弁天池の近くには「わらべ地蔵」と称される小さなお地蔵さまたちが佇んでおり、夏には苔の緑がお地蔵さまの美しさを引き立てます。
また、紅葉の名所としても名高い三千院ですが、春の桜やシャクナゲ、初夏の新緑やアジサイ、冬の雪景色など、四季折々の風情が素晴らしいため、さまざまな季節に訪れてみてはいかがでしょうか。
| 所在地 | 〒601-1242 京都府京都市左京区大原来迎院町540 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-744-2531 |
| アクセス | 京都バス「大原バス停」下車、徒歩約10分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【開運】京都最古の禅寺と趣の異なる庭園、紅葉が彩る 「建仁寺」


「建仁寺」は、建仁2年(1202年)に創建され、京都における最古の禅寺として位置付けられています。
南側にある「勅使門(ちょくしもん)」は国の重要文化財に指定されており、その柱や扉には矢の跡が見られることから「矢の根門」または「矢立門」とも呼ばれています。この勅使門は平重盛の六波羅邸の門、もしくは平教盛の館門を移建したものといわれています。
本坊には国宝である「風神雷神図屏風」を精巧に再現したデジタル複製画が展示されており、写真撮影も可能です。ほかにも、法堂の天井には創建800年を記念して約108畳分の広さに描かれた「双龍図」があり、その迫力に圧倒されます。
境内には、「大雄苑(だいおうえん)」、「潮音庭(ちょうおんてい)」、「〇△□乃庭(まるさんかくしかくのにわ)」の異なる趣を持つ3つの庭園があり、それぞれの庭園を眺めながらゆったりとした時間を過ごすことができます。
特に、潮音庭のいろは楓やドウダンツツジが赤や黄色に色づく秋は、圧巻の美しさです。例年の見頃は11月下旬から12月上旬ですので、紅葉を楽しみたい方はこの時期に訪れるとよいでしょう。
また、毎月第2日曜日には、坐禅体験(※参加費無料・予約不要)が実施されているほか、約60分の写経体験(※受付は午前10時~午後3時、有料、予約不要)も行われていますので、ぜひ体験してみてはいかがでしょうか。
| 所在地 | 〒605-0811 京都府京都市東山区大和大路通り四条下る小松町584 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-561-0190 |
| アクセス | 京阪本線「祇園四条駅」下車、徒歩約7分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【魔除け・厄除け】安倍晴明公を祀り平安の祈りが息づくパワースポット 「晴明神社」


「晴明(せいめい)神社」は、平安時代中期の著名な天文学者である安倍晴明公を祀る神社で、寛弘4年(1007年)に創建されました。一の鳥居には、金色に輝く社紋「晴明桔梗」が掲示されています。「五芒星(ごぼうせい)」とも称される晴明桔梗は、陰陽道の呪符や家紋に用いられる文様で、鳥居の額部分に神社や神様の名前ではなく社紋を掲げるのは全国的にも珍しく貴重です。
境内には、晴明公が念力を使って湧き出させたと伝えられている「晴明井」と呼ばれる井戸があり、湧き出す水は病気平癒のご利益があるとされ、現在でも飲用可能です。水源がその年の恵方を向いているため、吉祥の水を得ることができるともいわれています。
また、魔除けや厄除けの果物とされる桃の形をした「厄除桃(やくよけもも)」は、撫でることで厄が落ち健康になると信じられています。さらに、樹齢約300年と推定されるクスノキが御神木として祀られており、こちらも触れることでご利益が得られるとされています。
晴明公を祀った本殿は、境内の最も奥まった場所に位置しており、随所に晴明桔梗が施されたその姿は荘厳で参拝者を神聖な雰囲気へと誘います。
※授与所営業時間 9:00~16:30
| 所在地 | 〒602-8222 京都府京都市上京区晴明町806(堀川通一条上ル) |
|---|---|
| 電話番号 | 社務所:075-441-6460(9:00~17:00) |
| アクセス | 京都市営バス「一条戻橋・晴明神社前」下車すぐ |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【厄除開運】霊水が湧き出る八幡造りの荘厳な社殿 「石清水八幡宮」


「石清水八幡宮」は、日本三大八幡宮のひとつで、古くから「やわたのはちまんさん」として地元民に親しまれててきました。清和天皇の命により平安京の裏鬼門を守るために八幡大神を男山に祀り、社殿を建立したことを起源とします。開運厄除、心願成就、学業成就、勝運などのご利益があるとされ、多くの参拝者に人気です。
平成28年(2016年)に国宝に指定された朱塗りの社殿は豪華絢爛で、内殿と外殿の前後二棟からなる「八幡造り」の建築様式は、現存する八幡造りの社殿の中で最大最古といわれています。山全体が境内であり、社殿は山の上に位置しているため、参拝の際はケーブルカーを利用するとよいでしょう。
また、清和天皇は源氏一門の祖であり、八幡大神が源氏の氏神であることから、戦国時代には多くの武将たちがこの地を訪れ、勝利を祈願したと伝えられています。本殿の内殿と外殿の間には織田信長公が寄進したといわれる「黄金の雨樋(あまどい)」があり、必見です。
参道には史跡が点在しているので、参拝後は徒歩で下るのもおすすめです。参道には、石清水八幡宮の名前の由来にもなった「石清水社」があり、そこに湧き出る霊泉「石清水」は干ばつ時にも枯れることなく厳冬期にも凍結しなかったことから、パワースポットとして人気を集めています(※現在は水を飲むことができません)。
※黄金の雨樋は、土日祝の14時からの昇殿参拝(1人1,000円)に当日申込をされた方がご覧になれます。
| 所在地 | 〒614-8588 京都府八幡市八幡高坊30 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-981-3001 |
| アクセス | 京阪電鉄本線「石清水八幡宮駅」より参道ケーブル「八幡宮口駅」~「八幡宮山上駅」下車、徒歩約5分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
こちらの記事では、京都土産におすすめの
お菓子や雑貨をご紹介しています。
【開運】雲龍図の迫力と広大な庭園の世界遺産 「天龍寺」


「天龍寺」は、臨済宗天龍寺派の大本山であり、足利尊氏が後醍醐天皇の冥福を祈って後嵯峨上皇の亀山殿跡地に創建した由緒ある寺院です。1994年には、世界遺産「古都京都の文化財」のひとつとして登録されました。
天龍寺は開運のパワースポットとしても知られ、多くの参拝者が訪れます。特に注目すべきは、法堂の天井に描かれた巨大な「雲龍図」です。360度どこから見ても龍が睨んでいるように見えることから「八方睨みの龍」と呼ばれ、天龍寺開山夢窓国師650年遠諱(おんき)記念事業として、日本画家の加山又造画伯によって描かれました。その迫力ある姿は見る者に強い印象を与えます。
さらに、庫裏(くり)の正面玄関に置かれた衝立には、平田精耕前管長筆の力強い表情が特徴的な「達磨図」が掲げられており、天龍寺を代表する画として知られています。
また、庭園の四季折々の美しさも魅力です。春は桜、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色と、いつ訪れても美しい景観を楽しむことができます。特に、多宝殿付近の枝垂れ桜や池に移った紅葉は大変美しく、心が癒されることでしょう。
| 所在地 | 〒616-8385 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-881-1235(8:30〜17:00) |
| アクセス | JR「嵯峨嵐山駅」下車、徒歩約13分 京福電鉄嵐山線「嵐山駅」下車すぐ |
|
※参拝料や参拝時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
樹齢400年以上の巨木と極楽浄土を思わせる御影堂が迎える 「西本願寺」

「西本願寺」は浄土真宗本願寺派の本山であり、正式名称を「龍谷山本願寺」といいます。地元の人々からは「お西さん」と親しみを込めて呼ばれる存在です。
注目すべきは、入母屋造りと本瓦葺きを特徴とする「御影堂」で、南北62m、東西48m、高さ29mという壮大な規模を誇っています。これは現存する江戸時代の建築物のうち最大級の規模で、一度に1,200名以上が参拝できるといわれるほどです。内部には、約14万枚もの金箔を使った煌びやかな装飾が施されており、まるで極楽浄土に足を踏み入れたかと錯覚するほど荘厳で美しい光景が広がっています。
御影堂の前に立つ巨大な銀杏の木は樹齢400年以上といわれ、その場所一帯にエネルギーを宿しているような雰囲気があります。手を合わせると、心が洗われるような気持ちになるという声も聞かれます。
境内には壮麗な建築物がいくつも点在しており、数多くの国宝が納められていることも西本願寺の魅力です。なかでも「唐門」は、桃山時代を象徴する豪華絢爛な装飾が施されており、日が暮れるのを忘れて見とれてしまうほどの美しさから、「日暮らし門」とも呼ばれています。
| 所在地 | 〒600-8501 京都府京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-371-5181 |
| アクセス |
京都市営バス「西本願寺前」下車すぐ 京阪バス「西本願寺」下車すぐ |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【金運】黄金の鳥居と福包み守りがツキを呼び込む 「御金神社」


「御金(みかね)神社」は、ビルやマンションが建ち並ぶ京都の中心地にあるアクセス良好な神社で、金運アップにご利益があることから全国各地から多くの参拝者が訪れます。主祭神は、金属と鉱物の守り神である「金山毘古命(かなやまひこのみこと)」で、金運・招福、商売繁盛、宝くじなどお金にまつわるご利益があるとされています。
まず、参拝者の目に飛び込んでくるのが神社の入口に建つ「金の鳥居」で、その黄金色に輝く姿はまるで金運の象徴のようです。また、社殿の前には特別に作られた「金の鈴緒(すずのお)」があり、参拝者の金運アップへの期待をよりいっそう高めます。
境内にある授与所では、御神木である銀杏の葉をモチーフにしたお守りや絵馬などが多数授与されています。金運アップを願う人には「福包み守り」がおすすめで、通帳や新札、宝くじなど、自分にとって大切なものを入れておくことで金運を引き寄せるといわれています。職人の手によって一つひとつ金の箔押がされており、売り切れになる日もあるほどの人気です。
ほかにも、お財布や鞄などに入れておくことができる「おたから小判」や「カード守り」、がま口をかたどったストラップ付の「大金守り」などもあるので、「福包み守り」とともに身に付けて、さらなる金運アップの願いを掛けてみてはいかがでしょうか。
| 所在地 | 〒604-0042 京都府京都市中京区西洞院通御池上ル押西洞院町614 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-222-2062 |
| アクセス | 地下鉄「鳥丸御池駅」下車、徒歩約5分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
京都の御朱印については
こちらの記事でもご紹介しています。
【健康】阿呆賢さんに願いをこめる 「今宮神社」


「今宮神社」は、正暦5年(994年)、都で猛威を振るっていた疫病の平癒を祈るために創祀された由緒ある神社です。今宮神社には「本社」や「疫社」をはじめとする多くの社が鎮座し、それぞれ異なる御祭神が祀られています。
本社には、「大己貴命(おおなむちのみこと)」、「事代主命(ことしろぬしのみのこと)」、「奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)」の三柱が祀られており、厄除健康長寿のご利益があるとされています。
疫社は、平安遷都以前からこの地にあった古いお社で病気平癒のご利益があるとされています。さらに、疫社の西側にある「織姫社」には、機織りの神である「栲幡千千姫命(たくはたちぢひめのみこと)」が祀られています。この神は七夕の織姫に機織りを教えたとも伝えられており、機織りやものづくりなどをしている方がその技術向上を祈願するために足を運びます。
境内の一角には「阿呆賢さん(あほかしさん)」と呼ばれる霊石が置かれていて、この石をそっと撫でてから自分の体の悪い部分をさすると快方に向かうと昔から言い伝えられています。また、願い事の成否を占うことができる「神占石(かみうらいし)」でもあるので、ぜひ願い事がある方は立ち寄ってほしいスポットです。
また今宮神社では、春のさきがけをなす祭として毎年4月の第2日曜日に、悪疫退散を祈願するお祭り「やすらい祭」が執り行われており、季節の風物詩のひとつとなっています。
| 所在地 | 〒603-8243 京都府京都市北区紫野今宮町21 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-491-0082(受付時間:9:00~17:00) |
| アクセス | 京都市営バス「今宮神社前」下車すぐ |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【方除】源氏物語ゆかりの庭園が美しい平安京の守護 「城南宮」


「城南宮」は、平安遷都の際に都の安泰と国土の守護を願って創建され、城(平安京)の南にあることから「城南神」とも呼ばれています。特に方除(ほうよけ)の御神徳として知られており、旅行や交通安全、引越し、工事安全などを願うために多くの参拝者が訪れ、篤い祈りを奉げます。
また、境内に広がる城南宮の神苑「楽水苑」には、「源氏物語」に描かれた80種あまりの草木が植えられており、「源氏物語花の庭」として人々に親しまれています。四季折々の花や紅葉を楽しむことができ、特に春先にはしだれ梅と椿が咲き誇り、素晴らしい景色を堪能することができます。この庭園では、毎年4月29日に、奈良時代から平安時代にかけて宮中で行われていた歌会を再現した「曲水の宴」が催されます。鳥を象った羽觴(うしょう)の上にお酒を注いだ杯を乗せて、庭園の小川に流します。それが自分の前を通り過ぎる前に和歌を詠むという雅やかな行事で、まるで平安の絵巻を目の前で見ているかのような雰囲気を味わうことができるでしょう。
| 所在地 | 〒612-8459 京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町7番地 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-623-0846 |
| アクセス | 地下鉄「竹田駅」下車、徒歩約15分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【学業成就・芸能】祈念神石が導く願いの成就、芸能人も訪れるパワースポット 「車折神社」


「車折(くるまざき)神社」は、平安時代後期の儒学者である清原頼業(きよはらのよりなり)を主祭神として祀る神社です。学業成就、試験合格はもとより、強く念じれば「約束を違えない」神様として信仰があり、商売繁昌・会社隆昌、金運・財運向上、良縁成就・恋愛成就といった多岐にわたるご利益があるとされています。
車折神社は石に対する信仰が篤く、境内にある「清めの社」には、石をかたどった円錐形の立砂が祀られています。悪運を浄化するパワースポットとして人気があり、スマートフォンの待ち受け画像にすると運気が上がるといわれています。
車折神社で特に有名なのが「祈念神石(きねんしんせき)」と呼ばれるパワーストーンです。この祈念神石には「おまもり型」と「おふだ型」の2種類があり、社務所で授かることができます。祈念神石を両手で包み、本殿前でご祈願後、おまもり型は毎日持ち歩くことで、おふだ型は神棚にお祀りすることで、あらゆる願いを叶え、悩みを解決へと導くといわれています。願いが成就したら、自分で拾った石に感謝の気持ちを記し、お礼参りで石塚に供えるのが習わしです。拝殿前には、願いが叶ったお礼として奉納された石の山があり、その信仰の深さを物語っています。さらに境内に鎮座する「芸能神社」には、芸能・芸術の祖神とされる「天宇受売命(あめのうずめのみこと)」が祀られており、境内を囲む朱色の玉垣には、訪れた多くの芸能人たちの名前が刻まれています。
| 所在地 | 〒616-8343 京都府京都市右京区嵯峨朝日町23番地 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-861-0039 |
| アクセス | 京都バス「車折神社前」下車すぐ 嵐電「車折神社駅」下車すぐ |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【お酒の神】延命長寿の霊泉と醸造の祖神を祀る 「松尾大社」


松尾大社(まつのおたいしゃ)は、大宝元年(701年)に創建された京都で最も古いといわれる神社です。現在の御本殿は室町時代初期に創建され、重要文化財に指定されています。本殿の屋根は、棟(むね)を箱形に覆い、棟端が唐破風形の「箱棟(はこむね)」、前後に同じ長さをしている「両流造(りょうながれづくり)」が珍しく、別名松尾造りと称され、本殿を横から見るとその造りがよくわかります。
御祭神に「大山咋神(おおやまぐいのかみ)」と「市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)」を祀っており、京都洛西地域を守護する総氏神として、古くより地域住民から厚い崇敬を受けてきました。開拓、治水、土木、建築、商業、文化、寿命、交通、安産など、そのご利益は多岐にわたります。なかでも醸造祖神、酒造の神様としての信仰が篤く、酒だけでなく味噌や醤油、酢といった発酵食品の製造・販売に携わる人々が全国から参拝に訪れます。
霊亀の滝の手前には「亀の井」という霊泉があり、この水を使うと酒が腐らないとされ、酒の元水として造り水に混ぜて用いる酒造家も多いそうです。また、この霊泉の水は延命長寿・蘇りの水としても有名で、早朝から開門と同時に汲みに来る人も多く見られます。
また、境内には、昭和を代表する庭園家・重森三玲が手掛けた3つの庭園があり、訪れる人の目を楽しませています。
| 所在地 | 〒616-0024 京都府京都市西京区嵐山宮町3 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-871-5016 |
| アクセス | 阪急電車「松尾大社駅」下車、徒歩約3分 京都市営バス・京都バス「松尾大社前」下車、徒歩約3分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【諸願成就】四柱の神々と霊石の力が守護する 「平野神社」


「平野神社」は、延暦13年(794年)に創建された歴史の深い神社です。御祭神は、源気新生・活力生成の神「今木皇大神(いまきすめおおかみ)」、竈(かまど)の神・生活安泰の神「久度大神(くどのおおかみ)」、邪気を振り開く平安の神「古開大神(ふるあきのおおかみ)」、生産力の神「比売大神(ひめのおおかみ)」の四柱で、総合運、全体運、諸願成就のご利益があるとされています。
平野神社の境内には、樹齢400年を超える御神木のクスノキと「すえひろがね」と呼ばれる霊石があり、パワースポットとして注目を集めています。すえひろがねは、「餅鉄(べいてつ)」とも呼ばれる強い磁力を持つ特殊な石で、その不思議な霊力から「鉄尊(てっそん)様」として古来より崇められてきました。「授かる守」という磁石入りのお守りに、願いを込めながらすえひろがねにくっつけると、石の持つ霊力がお守りに宿り、持ち帰ることができるといわれています。
また、平野神社は桜の名所としても有名で、境内の桜苑にはさまざまな種類の桜が植えられています。春に境内一帯が桜で埋め尽くされる光景は圧巻です。
| 所在地 | 〒603-8322 京都府京都市北区平野宮本町1番地 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-461-4450 |
| アクセス | 京都市営バス「衣笠校前」下車、徒歩約3分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【勝運】皇室ゆかりの古社で12柱の神々を祀る 「藤森神社」


「藤森神社」は、約1800年前に神功皇后によって創建された皇室ともゆかりの深い古社です。本殿は、東殿・本殿中央・西殿の三座から成り、御祭神には「素盞嗚尊(すさのおのみこと)」、「神功皇后(じんぐうこうごう)」など12柱の神々が祀られています。
藤森神社では、毎年5月1日から5月5日にかけて「藤森祭」が行われることから菖蒲の節句発祥の神社としても知られ、「菖蒲」は「尚武」に通じ、「尚武」は「勝負」に通じることから、勝運を呼ぶ神として信仰を集めてきました。また、5月5日には駈馬神事(かけうましんじ)が奉納されることから、馬の神としても崇められ、多くの競馬関係者や競馬ファンが勝運を祈願しに訪れています。
紫陽花の名所としても有名で、6月ごろになると、境内に植えられた約3,500株の紫陽花が見事に咲き誇ります。さらに手水舎には紫陽花が浮かべられ、参拝者はこの時期ならではの花手水で手や口を清めることができます。
| 所在地 | 〒612-0864 京都府京都市伏見区深草鳥居崎町609 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-641-1045 |
| アクセス | JR「藤森駅」下車、徒歩約5分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
藤森神社については
こちらの記事でも紹介しています。
京都旅行にはJR東海ツアーズのプランがおすすめです。
【出世開運】豪華な唐門と豊臣秀吉公像が参拝者を迎える 「豊国神社」


「豊国神社(とよくにじんじゃ)」は豊臣秀吉公を祀る神社で、市民からは「ホウコクさん」の愛称で親しまれています。出世開運のご利益で知られていますが、そのほかにも厄除招福、良縁成就、商売繁昌といったご利益があるとされています。また、本殿の右隣に位置する「貞照神社(さだてるじんじゃ)」は秀吉公の正室である北政所おね様が祀られています。
豊国神社では、秀吉公の馬印が千成瓢箪(せんなりびょうたん)であったことにちなんで、手水舎にはひょうたんが用いられ、唐門の横にはひょうたん棚(春~夏)があります。また、ひょうたんをモチーフにした絵馬やお守りもあり、参拝者に人気です。
豊国神社の中でも参道の正面に建つ「唐門」は特に有名で、もとは秀吉公が築いた伏見城にあったものと伝わっています。左右が約6m、高さは約10.5mにも及ぶ壮大で豪華な装飾が特徴で、国宝にも指定されています。また、境内には秀吉公や豊臣家ゆかりの資料を展示・収蔵している宝物館もあり、歴史好きには欠かせないスポットとなっています。
| 所在地 | 〒605-0931 京都府京都市東山区大和大路通正面茶屋町 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-561-3802 |
| アクセス | 京阪電車「七条駅」下車、徒歩約10分 京都市営バス「博物館三十三間堂前」下車、徒歩約5分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
【学業成就・良縁】かわいいうさぎに願いを託す 「宇治上神社」


「宇治上神社」は、かつて宇治平等院の鎮守社とされ、世界遺産「古都京都の文化財」のひとつとして登録されている神社です。
境内には宇治七名水の中で唯一現存する「桐原水(きりはらすい)」が湧き出ており、参拝者が手を清めるための手水として使われています。国宝に指定されている本殿は、平安時代後期に造られた「五間社流造(ごけんしゃながれづくり)」の建築様式で、現存する神社建築としては日本最古といわれるものです。さらに、鎌倉時代に建てられた「神殿造」の拝殿も、国宝に指定されています。
御祭神には「菟道稚郎子命(うじのわきいらつこのみこと)」、父君の「応神天皇(おうじんてんのう)」、兄君の「仁徳天皇(にんとくてんのう)」の3柱が祀られており、学業成就、勝負運、縁結びなどのご利益があるとされています。
また宇治上神社がある宇治の地は『古事記』や『日本書紀』において「菟道」と書いて「うじ」と読まれていたこと、御祭神である「菟道稚郎子」の名前もこの地に由来し、「菟」の字が使われていることから、うさぎに縁深い神社としても有名です。うさぎをモチーフにしたカラフルでかわいらしいおみくじやお守りが授与されているので、お参りの際にぜひチェックしてみてください。
| 所在地 | 〒611-0021 京都府宇治市宇治山田59 |
|---|---|
| 電話番号 | 0774-21-4634 |
| アクセス | 京阪線「宇治駅」下車、徒歩約10分 |
|
※拝観料や拝観時間については公式ホームページなどでチェックしてください。 |
|
京都旅行を予約するならJR東海ツアーズの新幹線パックがおすすめ
京都の魅力をじっくり味わいたいあなたには「京都旅行」特集
神社や寺院など美しい景観であふれる古都・京都の魅力をもっと堪能しませんか?「EX旅パック」でおすすめの新幹線+ホテルのセットプランを予約!
まとめ
今回は、京都のおすすめの神社・寺院29ヶ所をご紹介しました。日本の歴史や文化を知るうえで欠かせない神社・寺院ばかりです。訪れれば、ご利益はもちろんのこと、歴史がつくりだす荘厳さとそれを取り囲む自然の優美さにきっと心が癒されることでしょう。
また、今回ご紹介した神社・寺院のほかにも、京都には魅力的な場所がたくさんあります。訪れるたびに新たな発見がある京都に、ぜひ何度でも足を運んでみてはいかがでしょうか。
※情報は2025年3月現在のものです。
※最新情報は各施設へお問合せください。
※画像は全てイメージです。
編集:JR東海ツアーズ